ローカル×海外の視点から読み解く「放送コンテンツの海外展開」〜著者対談インタビュー前編
ジャーナリスト 長谷川朋子
左から長谷川朋子氏、大場吾郎氏、永野ひかる氏
デジタル化とグローバル化が加速するメディア環境のなかで、佛教大学大場吾郎教授編著による最新本「放送コンテンツの海外展開―デジタル変革期によるパラダイム」(中央経済社)を上梓した。拡張する放送コンテンツの海外展開に着目し、その理論と実践の両方の視点から網羅的に考察する初の専門書になる。大場吾郎氏と共著した朝日放送テレビ総務局国際業務担当マネージャーの永野ひかる氏と筆者が執筆の意図とその背景について対談する機会を設けさせてもらった。前後編にわたってその内容をお伝えしたい。
【後編】アフターコロナを見据えた「放送コンテンツの海外展開」〜著者対談インタビュー後編
■網羅的にカバーした海外展開最新事情

長谷川:近年、放送番組の海外展開はパッケージされた番組を海外に売るいわゆる“海外番販(番組販売)”から様々なビジネスモデルで海外市場に流通させる“国際コンテンツビジネス”へと広がりをみせています。企画意図にはこうした背景も大きかったのでしょうか。

大場氏:放送コンテンツの海外展開はまさに拡張している分野です。だから、多様化している部分を“全部取り揃えました”という専門書があってもいいのでないかと思いました。ワンポイントを深く捉えるより、網羅的にカバーできるものが必要であると。これを一冊の本として成立させるために、専門的な知見がある方に声をかけさせてもらいました。この分野におけるオールスターチームの“侍ジャパン”だと自負しています。お一人でも欠けていたら試合にならなかったかもしれません。
長谷川:国際見本市を通じて追ってきたビジネスの変遷をまとめることができ、こちらこそ有難い機会でした。執筆陣は全8名。テーマ項目の主軸について改めてご解説いただければと思います。
大場氏:長谷川さんが担当した国際テレビ番組見本市についてはマーケットのメカニズムを含めて説明されているものです。朝日放送テレビご所属の永野さんにはキー局とは異なる取り組みがあるローカル局の海外展開について取り上げてもらいました。また、アニメのローカライゼーションや番組フォーマットセールスについて専門的な視点で考察している章もあります。そして、日本の放送コンテンツを海外で展開する際にボトルネックとなっていた著作権処理についても深掘できたと思っています。複雑だと言われている権利処理ですが、海外に限ってはどのような処理が必要なのか、それを具体的に解説している本は他にはないでしょう。いずれにしろ放送コンテンツの海外展開を取り組む際に前提として知っておくべきテーマ項目を選んでいます。
■資金やリソースもない放送局が海外とどう向き合っているのか
長谷川:準キー局、ローカル局が取り組む海外展開は今、多岐にわたっています。永野さんは御社をはじめ、在阪民放局の連携や大分朝日放送や山形放送の事例を紹介されていますが、どこに焦点を当てようと思われたのですか?
永野氏:キー局ほど資金やリソースもない放送局が海外とどう向き合い、考え、取り組んでいるのか。そこに焦点を当てています。海外展開のノウハウがなかった当社が取り組み始めた事例から、ローカル局が海外展開を始めるとっかかりとして参考にしてもらいやすいケースまで、紹介させてもらっています。

大場氏:実は今回の企画で最も取り上げたかったものは“ローカル×海外”の視点でした。キー局の海外展開は規模も大きく、注目が集まりやすいのは事実ですが、ここにきてキー局はキー局の、準キー局は準キー局の、ローカル局はローカル局のそれぞれ異なる広がりがみられます。つまり、それぞれ適切な海外展開のやり方があるということです。
長谷川:インバウンド需要の背景を解説した章から続く流れで、永野さんがご担当された章では放送局が取り組むインバウンド向けの海外展開についても触れていますね。これもまさに放送コンテンツの海外展開における広がりのひとつです。
永野氏:5、6年前からインバウンド向けの取り組みについて、系列の他局から相談を受けていました。局の規模とは関係なく共通するのは、やはりローカル局が海外とどのように向き合うべきかという点です。地上波だけではビジネスが立ち行かなくなっていることがその根底にあり、打開策のひとつとして海外との向き合いを考え始めていることがわかりました。だからこそ、その答えになることは必ず書きたいと思いました。
長谷川:大分朝日放送の事例紹介では、自社のブランディングとして海外展開に取り組まれていることがわかり、それも答えのひとつだということが理解できます。
■海外に向けて番組を作ることは財産にもなり得る
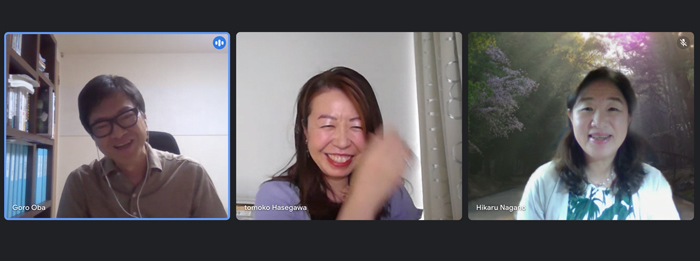
大場氏:大分朝日放送の事例が興味深い理由として、放送外にも目を向ける意識が高いということにあります。その取り組みのひとつとして、海外があったということです。老舗のラテ兼営局よりもいわゆる平成新局の方が海外展開を取り組みやすいという特徴があるのかもしれません。
永野氏:社風も大きいと思っています。経営陣が“面白いことをやってみよう”と先陣を切り、それに乗っかる社員がいる局は物事が転がっていることが多い。一方、経営陣が“どれぐらい儲かるの?”の問いかけから始まり、社員は社員で後ろ向きの反応を示す局もあると聞きます。
長谷川:インバウンド向けの取り組みは放送局の利益に直結しにくいこともあり、捉え方の違いが生まれているんでしょうね。
大場氏:それでもチャレンジしている局もあるのは、経験値を財産として蓄えることができるからだと思います。海外に向けて番組を作ることは、地域に向けて番組を作ることとは違う視点が必要になり、それが財産にもなり得る。その考え方のきっかけとして、この本がガイドラインとして機能することを目指しています。
近年、準キー局やローカル局の海外展開が顕著に広がっていることへの理解を深めるものとして、手前味噌ながらオススメしたい一冊である。また本書ではアフターコロナを見据えた海外展開についてもそれぞれのパートで見解を述べている。後編はこの話題を中心にお伝えする。
