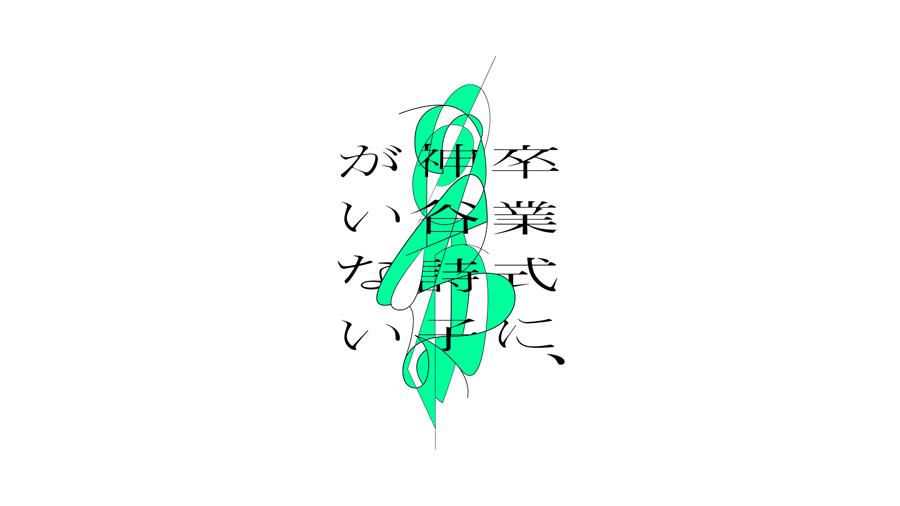テレビの連ドラ監督が挑む“Zドラマ”とは〜 日本テレビ『卒業式に、神谷詩子がいない』伊藤彰記監督(AX-ON所属)インタビュー
編集部
伊藤彰記氏
日本テレビは、モデルをはじめ、NHK連続テレビ小説への出演や、全国高校サッカー選手権の応援マネージャー就任など多方面で活躍する女優・茅島みずきが主演するZドラマ『卒業式に、神谷詩子がいない』を制作。2022年2月27日(日)から放送を開始した。
Zドラマとは、「Z世代に向けたエール」をコンセプトに、ドラマの世界観をメディアや手法にとらわれず、SNS、楽曲、ライブ配信、映画、舞台など自由なカタチで描き出すドラマプロジェクト。毎週日曜放送のドラマ本編とともに、放送前の月曜から土曜にかけて「かじるドラマ」と銘打った短尺の縦型ショート動画を各SNSで先行配信。出演者によるVlogや本編を濃縮した映像など、視聴者がスキマ時間を使って楽しめるコンテンツを届ける。
本作『卒業式に、神谷詩子がいない』は、家庭環境や中学時代のトラウマから明るい未来を描けずにいる主人公・神谷詩子(茅島みずき)を中心に、高校生の男女6人の青春群像劇を描くドラマ。『ハコヅメ!〜たたかう!交番女子〜』や『35歳の少女』など、日テレのヒットドラマを数多く手がけてきたAX-ONの伊藤彰記氏が監督を務める。

巷では"若年層のテレビ離れ"が叫ばれて久しいが、今回のプロジェクトにはどのような思いが込められているのか。Z世代にスポットをあてたコンテンツとして、演出面ではどのような点に力を入れているのか──。伊藤氏に話を聞いた。
■敬語禁止、アドリブ自由。“リアルZ世代”であるキャストの人柄をドラマに反映する
――「Z世代に向けたエール」をコンセプトに掲げる今回のプロジェクトですが、立ち上げにあたってはどのような背景があったのでしょうか。
伊藤監督:若者におけるテレビ離れもその一端にはありますが、もっとも大きな背景は、いまもまだ終わりの見えないコロナ禍です。高校生をはじめ、10代の若者たちが参加するいろいろな大会や学校行事がコロナの影響によって中止を余儀なくされているというニュースを私たちも数多く目の当たりにしてきました。
そんななか、彼らに何かしらのかたちでエールを送ることができないか、という思いから、今回のプロジェクトが立ち上がりました。私もその一員として、さまざまな取り組みを考えています。
――これまでも多くのヒットドラマを手がけてきた伊藤監督ですが、今作へ臨むにあたって、どのようなことを念頭に置きましたか。

伊藤監督:今回、ドラマは地上波で日曜昼に放送されていますが、現在はTVerをはじめ、さまざまな媒体でテレビ番組が見られていますし、実際にはゴールデンタイムのドラマと横並びの状態から、視聴者のみなさんに選ばれなくてはいけません。今作のキャスト陣がゴールデンの出演陣に魅力の面で勝つためにどうしたらよいかと考えたとき、彼らが持つ10代のパワーや純粋さを大事にすべきではないかと思い至りました。
――制作現場では、具体的にどのようなアプローチを取っていますか。
伊藤監督:私自身は「こんなことをしたい」と、あらかじめ演出プランをしっかり固めて現場に入りますが、キャストたちには「自分の判断でセリフや動きを替えてもいいよ」と伝えています。台本の台詞がすべてではないし、自分たちが役に落としたときにしゃべり方や動きが変わることもあるでしょう。「この台詞が言いづらい」ということも全然言ってくれてかまわないと伝えています。
――実際にZ世代の若者であるキャストのみなさんの魅力を活かしているのですね。
伊藤監督:10代の子たちが自然に感じることや言葉遣いといったものを大事にするためには、まずはキャストのみなさんが思うままに演じてもらい、それが自然に見えたらOK、というスタンスをとりました。
シーンの狙いが回収できていれば、あらかじめ決めたカット割に沿っていなくてもOK。演技が自然で良ければ、あとはどのように撮影してシーンを組み立てていくか、カメラマンと相談していこうと。キャストの演技に自由度を与えるという点をとくに意識して進めていました。
――撮影にあたり、キャストのみなさんにはどのようなリクエストを出しましたか。
伊藤監督:彼らがもともと持つ純粋さや爆発力を引き出したかったので、撮影をはじめるにあたり、「キャスト同士では敬語を使わないこと」というルールを設けました。
ドラマのうえでは同じ高校生役を演じるキャスト陣ですが、実際の年齢は17歳から24歳までと、かなり幅があります。社会人にとっての2, 3歳差と高校生にとっての2, 3歳差は全然違いますし、最初のリハーサルでも、そうした感覚から来る遠慮や緊張感が漂ってしまっていたので、キャストの6人に「敬語禁止令」を出しました。
――「敬語禁止令」の効果はいかがでしたか。
伊藤監督:6人がドラマの役柄を超えて本当に仲良くなったことで、台本では直接表せない、お互いの関係性の表現にぐっと説得力が加わりました。
今回の台本には、「みんな盛り上がる」というように、ト書きだけの指示が結構あるのですが、すでにキャスト同士の関係性が出来上がった状態なので、私からは「じゃぁ、あとはよろしく」と、全部お任せしています。
あとはこちらから何も言わなくても、みんな自然と“盛り上がって”いきます。本心からの感情だから、自由な言葉がたくさん出てきて、リハーサルと本番で毎回台詞も違う。それがすごく良いんです。
――キャストのみなさんの人柄が、ドラマにそのまま反映されているのですね。
伊藤監督:10代の子たちが笑う様子って、すごくパワーがあるなと思っていて。そこを演技してしまうと、やっぱり「笑っているような芝居」で終わってしまうんですよね。
ある日、主人公・神谷詩子を演じる茅島みずきさんから、「私のキャラクターとして、こんなに笑ってしまっていいんですか?」と相談をされました。私としては、みんなが見せた表情そのものがドラマになると思ったので、「茅島さんが出すものは、すべて詩子になる」と伝えました。「詩子だから、こうしてはいけない」と考えるよりも、一瞬、素の茅島さんが出ても良いから、それを詩子だと思うレベルまで持って行きたいなと。
もちろん、みなさん台詞を覚えてきて、ちゃんと演じてくれるのですが、今回のドラマでは“演じる“先に生まれる言葉や表情こそが一番大事であり、他のドラマと比べて勝負できるところなのではないかと思っています。
■ジェットコースター的な展開にしない。シーンを厳選し「狭くても深く刺さるドラマ」に
――30分という比較的短い分数でドラマを構成するにあたり、構成や編集の面ではどのような点に注力しましたか。
伊藤監督:限られた分数で3年間の高校生活を描くため、シーンを削ってドラマとしての純度を高めていくことに注力しました。すべての展開を拾っていっていてはストーリーを回収しきれませんし、見る人にとっても、どのシーンに着目すべきかがわからなくなってしまう。ストーリーのうえで、何を中心に見せたいかということを主軸においたうえで、もともと台本に書いていた展開もふくめ、かなりのシーンを取捨選択していきました。
――展開にスピード感を持たせるということでしょうか。
伊藤監督:単に途中でチャンネルを変えさせないという意味では、どんどんカットやシーンが変わるジェットコースターのような展開が良いでしょう。しかしそうなると、見終わった後、心に何も残らないのではないかという思いもありました。
30分という限られた分数のなかで、本当はテンポ早くストーリーを進めていきたいところでしたが、やはり見せるべきシーンをたっぷり見せるということは外したくありませんでした。薄く広く、ではなく「狭くても深く刺さるドラマ」に仕上げるため、編集での尺調整は非常に入念に行いました。
――差し支えなければ、具体的なエピソードを教えていただけますか。
伊藤監督:たとえば、劇中で6人で話すシーンがあります。それぞれ1人ずつのカットを撮影しておけば、編集でシーンの長さを柔軟に調整可能です。でも、6人の仲の良さを表現するためには、やはり全員が揃ったカットで見せたい。どこまで全員のカットを使い続けることができるか──。編集作業は、こうした“我慢”の連続でもありましたが、結果として、メリハリのある構成につなげられたのではないかと思っています。
■SNS動画専任の“Vlog班”を設置。Z世代向けのタッチポイントを増やす狙い
――今回は地上波のドラマ本編に加え、放送前にSNSを通じて短尺動画を毎日公開していく取り組みが行われていますが、地上波の映像とはどのように作り方を変えていますか。
伊藤監督:今回、本編の制作班とは別に専任のVlog班が稼働し、TikTokやInstagram、LINEなどのSNS用の動画撮影を行うほか、本編映像を独自に編集する体制を取っています。
これまでのドラマでは、現場スタッフが撮影の合間に簡単な動画を撮って公開するという形式が多かったのですが、今回は最初からZ世代に照準を絞り、本編内では表現しきれないキャスト個人や役の魅力に迫った動画や、本編で一部カットしたシーンのフル尺バージョンといった「刺さる映像」でZ世代へのタッチポイント増加を狙っています。
ひとつの映像を地上波、SNS用と切り出すだけではなく、ドラマ本編と並行しながら、ターゲットに特化した専用コンテンツを別途制作していくというアプローチは、地上波ドラマとしては非常に斬新な取り組みではないでしょうか。

【関連記事】日本テレビ、Zドラマ『卒業式に、神谷詩子がいない』の縦型ショート動画コンテンツをSNSで配信開始
――Z世代をはじめ、若者たちにおけるテレビ離れが議論となっています。このような現状を踏まえ、ドラマ制作者としてどのようなことを考えていますか。
伊藤監督:10代の若者たちに話を聞くと、「テレビドラマは見ていない」という一方、実際には「韓国のドラマやハリウッド映画をネットで見ている」という声が返ってきます。“ドラマ”そのものはいまもしっかり見られているのです。私たちは、こうしたコンテンツと横並びで競争をしなければならない状況にあります。
テレビ離れに対抗するとしても、逃げていった10代の人を呼び戻すだけでは、単に昔の状態へ戻るだけなのではないでしょうか。「Zドラマ」と銘打ち、10代の人々に向けて届けるならば、日本国内に限らず、世界の人に見てもらうことを意識していかなければならないと思っています。
海外であれば、出演俳優の知名度などに依存することなく、純粋に演技の魅力やドラマとしての面白さで勝負することができます。日本の高校の制服は世界でも人気がありますし、それをきっかけに広がるかもしれません。せっかくネットというツールがあるのですから、それをうまく活用して海外のZ世代にも注目してもらい、視聴者の分母を増やしていきたいと考えています。
■「コロナ禍も“青春の思い出”に昇華できるはず」ドラマを通じてZ世代に伝えたい思い
――かつて10代を経験した大人として、いまのZ世代にはどんなことを感じますか。
伊藤監督:コロナ禍のZ世代にエールを送りたい、という思いから立ち上がった今回のプロジェクトですが、はたから見ればつい「かわいそうだ」とばかり思ってしまいがちな現状も、もしかすると考え方次第でプラスにできるパワーを秘めているのではないかという気がしています。
経験できるはずであったことを経験できないのは、とても悔しいでしょう。でも同時にZ世代の人々は、そうしたことも含めて青春の一ページを作り出せるパワーを持っていると思うのです。いま、コロナ禍で抱えている悔しいという思いを、数年後、逆にいい思い出へと昇華してくれるのではないかという期待を抱いています。
――今回のドラマを通じて、Z世代のみなさんにどのようなことを伝えたいですか。
伊藤監督:ドラマを通じて、未来への希望を少しでも感じてもらえたらと思っています。
今回は高校が舞台の話ですが、実際の人生では、そこから社会に出ていく過程のなかで、世界が急速に広がっていきます。悪い方に考えればいくらでも悪い方に考えられると思いますが、良い方に考えれば、いくらでも良い方に考えられるとも思うのです。
高校の3年間で得た友達や経験というものは、大人になってから学校の勉強より大切なものになっているのではないでしょうか。みなさんが飛躍し、希望を持って進んでいくことで、未来が明るくなってくれたらと願っています。