放送のデジタル化は飛びあがるのか、徐々に移行するのか?「第2回マル研カンファレンス2017 ~ローカル放送局のAutonomy(自律)~」<vol.3>
編集部
2017年12月、マルチスクリーン型放送サービスの実用化を目指す「マルチスクリーン型放送研究会(マル研)」が、「第2回マル研カンファレンス2017 ~ローカル放送局のAutonomy(自律)~」を開催した。前回まではローカル局10社のプレゼンテーションの内容をレポートしてきたが、3回目となる今回は、慶應義塾大学環境情報学部教授・村井純氏の基調講演と、村井教授からの3つの質問をテーマとしたパネルディスカッションの様子をレポートする。
■日本語訳に捕らわれずに「ブロードキャスト」を捉えよう
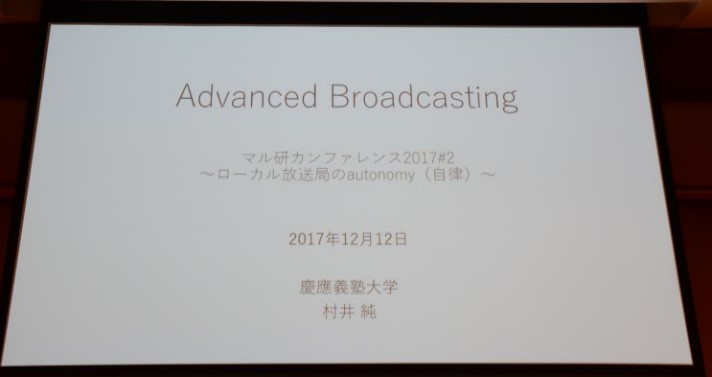
当たり前のように放送を意味する言葉として扱われている「ブロードキャスト」。しかし、「ブロードキャスト=放送」という定義は本当に正しいのだろうか。
 慶應義塾大学環境情報学部教授・村井純氏
慶應義塾大学環境情報学部教授・村井純氏村井教授は基調講演にあたって、「日本語訳の意味に捕らわれていないか」と一石を投じた。西洋文化が日本に流入した当時、様々な外来語が日本語に訳された。しかし、本来の意味とは違う訳語が充てられたために、世界が持っているストーリーとは異なる概念で理解されてきた言葉がある。
たとえば、慶應義塾大学創設者の福沢諭吉は、「エデュケーション=教育」と訳したが、本来の意味とはニュアンスが異なる。英語のエデュースには“ひっぱる”という意味があり、英語圏でエデュケーションは“人の中身を引き出すこと”と捉えられているのだ。ところが日本語の“教えて育む”と書く「教育」は、サプライサイド(与える側)の意味しか持たない。言葉の捉え方が違えば印象も変わり、実は世界との意識に差ができている可能性がある。村井教授は「エデュケーション=教育」を例に指摘した。
放送の話に引き戻すと、英語でブロードキャストは、“全員に伝える、全ての人に必ず届ける”という意味だ。「日本語訳の概念とそれほど離れてはいない(村井教授)」が、将来の放送局のビジネス展開を考えるなら、改めてブロードキャストの意味を捉え直すことも大切という。放送業界は広告収入で成り立つが、通信との融合によって新しいマネタイズが生まれるチャンスもある。電波による放送にとどまらず通信を利用すれば、本来の役割をもっと強化できるかもしれない。
「インターネット」も日本語と英語では印象が異なる。英語で表記すると「The Internet」または「The Net」となり、それぞれIとNがキャピタライズ(先頭の文字が大文字になっているという意味)されている。村井教授いわく、「キャピタライズされている言葉は地球上で1つしかない」そうだ。つまり、英語圏でインターネットは、「国境を越えた1つの(唯一の)グローバル空間」と認識されているということだ。村井教授は、「放送とデジタルネットワークが合成された時、放送のビジネスも国境を越えていくものだと考える必要がある」と語った。
■デジタルコミュニケーションにおけるマーケットはアジアにある!

グローバル化が基本のデジタルコミュニケーションにおいて、マネタイズを考えるならどの地域を狙えばよいのか。インターネット人口の推移を見ると、2000年は世界の全人口の6%(1位アメリカ、2位日本)だったのが、17年後の今年は51.7%にまで広がり歴史的な年となった。全世界でインターネット普及率100%を目指す中で、現状マーケットに伸びしろがあるのはアジアだけである。村井教授は、「デジタルコミュニケーションのマーケットはアジアしかない。(コンテンツなどを)ここで売れば勝てる」と、参加者に力強く述べた。
デジタル化においては、「ビヨンド・ザ・ボーダーで、縦が横につながるコラボレーションがイノベーションを生み出す(村井教授)」ことを視野に入れ、産業領域の異なるものが力を合わせれば、新しい産業が生まれる可能性がある。また、デジタル化によってプラットフォームが整備されれば、出口を放送や出版などと1つにくくる必要はない。テレビ、スマートフォン、雑誌、商品パッケージ、ラッピングバスなど、メディアコンテンツをマルチユースすることが標準化すればコスト面でも楽になるはず。「他局との競争領域や出口は放送だけではない。放送局は才能の宝庫だが、才能は1つではない」(村井教授)。
■放送のデジタル化は飛びあがるのか徐々に移行するのか
では放送のデジタル化への移行をどのように進めていくべきなのか。「アナログから地デジへは思い切ったジャンプで変わったが、放送のデジタル化にはマーケットの状況やレギュレーションが関わってくる」と村井教授はいう。また、村井教授のいう「Transition and Transformation」がキーワードで、放送のデジタル化は、徐々に変える部分と一気に変える部分が混ざり合いながら進むのかもしれない。
最後に村井教授は(自身も関わった地デジ推進用のキャラクター「地デジカ」を用いて)、「1次産業、2次産業、3次産業をかけ合わせれば、1×2×3=6で6次化する。産業領域や国境を越えて協力し合えば放送業界だけでなく産業全体が変わり、グローバル・テクノロジーで地球を変えることにもつながる。デジタル化によって進化する放送業界の未来が楽しみだ」と語り、基調講義を締めくくった。

■パネルディスカッション
 村上圭子氏(左)、齊藤浩史氏(右)
村上圭子氏(左)、齊藤浩史氏(右)第3部の後半では、基調講演を踏まえて、村井教授からの3つの質問を元にパネルディスカッションを展開。進行は齊藤浩史氏(毎日放送)、村上圭子氏(NHK放送文化研究所)。
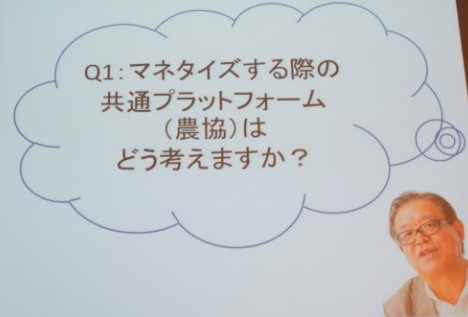
 服部弘之氏
服部弘之氏まず、村井教授から「マネタイズする際の共通プラットフォーム(農協)は、どう考えますか?」というお題が出され、これに対し、服部弘之氏(TOKYO MX)は、「これまで放送局がテレビというプラットフォームを使って連携してきたように、同時配信などを1社で進めるのではなく、エムキャス、ハイコネ、シンクキャストなどのプラットフォームを提供することで、いろいろな放送局と連携して展開していくことを目指している」と。
 浅井隆士氏
浅井隆士氏これに関して、奈良テレビはそのプラットフォームにのっかった立場。村上氏からどう考えているかと聞かれ、浅井隆士氏(奈良テレビ)は、「マネタイズには、テレビの延長戦上のマネタイズと、まだ実現できていない分野でのマネタイズの2つがあると考えている。エムキャスで動画にCMをつけて配信するのはテレビの延長線上でのマネタイズで慣れているが、インターネット等を活用して新たなマネタイズをするには物凄くローカルの事情も絡んできて難しい。よってプラットフォームビジネスは困難だと考えている。マネタイズにはこの2つをどう整備していくかが今後の課題だ」と答えた。
 古賀健介氏
古賀健介氏古賀健介氏(名古屋テレビ)は、村井教授の問いかけに対し、「競争と協調が大切。民放ではスポンサー獲得など狭い領域での競争しかしてこなかったが、これからは一人ひとりの視聴者に向き合っていかなければならない。競争するのはコンテンツだけに留めて、放送局同士で協力できるところは協力し、他の領域の企業とも連携していくことが大切だ。スマートフォンアプリも乱立して過渡期にあるが、何が残り、何と組むかを見極める必要がある。知恵を絞り、情報共有する場(プラットフォーム)としてマル研は役立っている」と。
そこで村上氏は、「競争と協調という話が出たが、放送局は市場の速さについていけるのか?」と疑問を。村井教授は、「競争と協調でいうと、放送業界は実はマネタイズ方法や方式、協調するものだらけ。競争する場は、番組作りの分野で番組の品質で勝負するしかない。しかし、競争領域を狭める必要はなく、放送局ができることは多い。最近の小学生の文化祭の出し物では、動画撮影した“ドラマ”を放映したりする。なぜ作れるのかというと、テレビを見ているからだ。テレビの影響力はこういうところにも表れている。今まで気が付かなかったところに競争領域があるかもしれない」と意見した。
 阿部洋樹氏
阿部洋樹氏続けて、村上氏は「ネット上で新しい価値を生むビジネスモデルを構築できるようなプラットフォームの姿をイメージするのが難しい。こういうことを実施している放送局はあるのだろうか?」と。 これに対し、阿部洋樹氏(テレビ大分)は、「J:COMと連携することに対して当初は不安があったが、ふたを開けてみれば上手く連携できている。コンテンツの出口のひとつとして、ケーブルテレビと仲良くしていくことも大事だと考えている」と語った。
 片山裕太氏
片山裕太氏片山裕太氏(広島テレビ)からは、「VRは間違いなく新しいフォーマットになる。VRの映像をデータベース化してアーカイブ化しておけば、将来的に引き合いがあるはず。たとえば旅行会社がツアーを組む場合、紙やWEBだけでなくVRもひとつの手法となる。地域の観光資源も活かせる。VRのプラットフォームをつくることで、新しい収益を期待できるのではないか」と話した。
ここで、村上氏は「マル研から共通プラットフォームが生まれつつあるように思える」と話が進められ、加えて齊藤氏が、「他県からロケに行くよりも、地元情報に強いローカル局の方がよいものを取れるのは当然。ローカル局が情報やコンテンツを提供できる共通のプラットフォームがあれば、足し算ではなく掛け算の、垣根を超えた新しい価値が生まれるかもしれない」。しかし、村上氏から「BtoBのプラットフォームはあるが、BtoCのプラットフォームが見えてこない。もっとユーザーに見えるプラットフォームサービスはないのか?」という指摘がなされた。
 俵積田邦夫氏
俵積田邦夫氏これについて、俵積田邦夫氏(南日本放送)は、「インターネットなどのIT技術によるメリットは、他企業とのアライアンスを加速させていること。弊社では地域のFM局やケーブルテレビと上手く連携できており、壮大なプラットフォームを実現できると考えている。しかし、マネタイズという意味ではまだ答えが見つからない。地域に住む人ときちんと向き合うことで、答えが見えてくるのかもしれない」と。
ここで、村井教授から「マネタイズとプラットフォームについて2つ提案がある。1つは、個々に視聴者データを収集しても個人情報が関わるので使いにくいが、視聴者データをアノニマイズしてフィードバックするプラットフォームがあれば、便利な上マネタイズの可能性も見える。もう1つは、地方の高校野球や高校相撲大会などの映像は、好きな人にとってはお宝コンテンツ。地方の放送局もケーブルテレビも映像を持っているはずなので、全国の映像をまとめるプラットフォームがあれば、マネタイズの可能性も広がるのでは」と述べた。
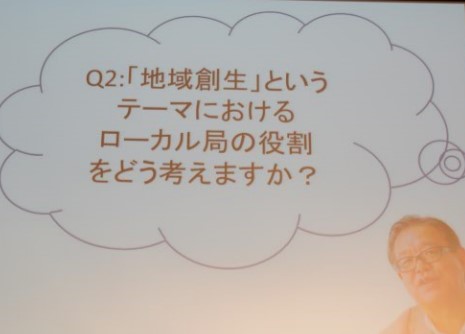
続いて、「地域創生」というテーマにおけるローカル局の役割をどう考えますか? というお題に移行。
 筒井規夫氏
筒井規夫氏筒井規夫氏(山陽放送)は、「地域が自立していくために、祭りの様子や地域の魅力をローカル局が発信していくことが求められている。街づくりに賛同する地元企業の皆さんと一緒に、地域に向き合って活動していくことが必要だと考えている」。
 越智俊貴氏
越智俊貴氏越智俊貴氏(テレビ埼玉)は、「地域の人にどう見てもらうのか、どう貢献できるのかを考えている。たとえば高齢者が増える中で、放送局としてどう役割を担っていくべきか。現在、麻雀教室などを開催していく予定だが、地域へ貢献できることをこれからも実施していくつもりだ」と述べたところで、村井教授は「地方放送局が地域創生のリーダーになるべき。知事以外に地域のことを深く考えられるのは、中小企業か観光業かメディアのみ。全てをプロデュースできるのはメディアしかない」とした。
 工藤健太郎氏
工藤健太郎氏工藤健太郎氏(仙台放送)は、「仙台、宮城県は支店経済都市と言われている。転勤で訪れては戻り、各県から大学に来ては就職で都会へ出て行ってしまう。宮城県ではU・Iターンに力を入れていて、いつか帰ってきてほしいという考えがあると思う。ローカルコンテンツを、出て行った人を含めて、県にゆかりのある人にリーチさせることは、地域創生にとっても重要なことだと考えている」と。
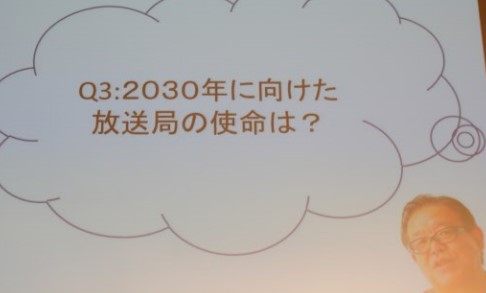
最後に、村井教授から「2030年に向けた放送局の使命は?」という質問が投げかけられ、静岡朝日テレビは、「地域のリーダーになれるのは、主に報道機関だと思っている。ニュースの信頼性は、圧倒的にテレビにあるが、県内の特定地域の情報を放送する場合、視聴者は自分の住むエリア以外の情報には興味が持てず視聴しないという実態がある。インターネットの普及が加速している現状で、放送局がこれまで以上に、誰がどこで何を見ているのかを正確に把握すべきだ」。
 服部氏
服部氏服部氏からは、「放送局は、今後、総合力が試される12年になるのではないかと思う」と述べられ、続けて筒井氏は、「ローカル局はコンテンツを作ってしていくしかないと思う。共通のプラットフォームで、動画をアップしたらテキスト化できたり、多方面の媒体に出してもらえたり、サポートしてくれるようなプラットフォームがあれば、ローカル局ももっとコンテンツ作りに集中していけると思う」。
 筒井氏
筒井氏また、加速度的に技術の進化が進む中、普及のスピードも速まっており、古賀氏は、「放送業界がどのように競争して、技術の進化を踏まえた上でどういうコンテンツができるのかを捉えることが業界としての使命だ。技術にどうキャッチアップしていくのかを考えることも、大事な要素だと思う。また、横連携しながら地域のリーダーやハブとなって地域を盛り上げることも大切だ」と考えを述べた。
 古賀氏
古賀氏それぞれの意見を聞いた後、村井教授は、「ブロードキャスティングは全員に届けること。ブロードキャスターには全員に届ける使命がある。他にこの役割を担うものはない。インターネットは基本的には基盤技術であり、インターネット上でやることはバラバラ。見る人は見るが、見ない人は見ない。地域のことを真剣に考えているのは知事と放送事業者のみ。全域を見るというブロードキャストの視点で、県民のことを深く知ってビジネスを作り出すことはカッコいいことだ。この国の未来を作るのはそこにある」と締めくくった。