吉本芸人に聞く「生き残り」のための動画戦略〜ブライトコーブ株式会社『REC ONE』レポート
マーケティングライター 天谷窓大
2019年9月4日、東京・渋谷のTECH PLAY SHIBUYAにてブライトコーブ株式会社主催のイベント『REC ONE』が開催され、動画メディアを中心としたコンテンツホルダーの担当者が「可処分時間の奪い方」をテーマに様々なトークセッションを繰り広げた。
本稿では、トークセッション『テレビなのか?ネットなのか? よしもと若手芸人に聞く“リアル主戦場”』の模様をレポートする。スピーカーは吉本興業所属の芸人で、お笑いコンビ「田畑藤本」の田畑勇一氏。
 田畑勇一氏
田畑勇一氏モデレーターを、ブライトコーブ株式会社 VP, Business Developmentの北庄司英雄氏、株式会社HEART CATCH代表取締役の西村真里子氏が務めた。
 北庄司英雄氏
北庄司英雄氏 西村真里子氏
西村真里子氏■YouTube配信で「ファンに向け、自分の得意な見せ方で勝負」
東京大学出身の藤本淳史氏とのコンビ「田畑藤本」は、“高学歴芸人コンビ”として人気を博し、今年で活動12周年を迎える。二人は吉本興業の育成組織「吉本総合芸術学院(NSC)」の出身だが、「同期でいまも芸能界に残るのは(全体の)10分の1程度」(田畑氏)と、その生存競争は熾烈だ。
そんな芸人たちのあいだで注目されているのが、YouTubeを通じた“ネタ”の発信という。

田畑氏:若手芸人がYouTubeを通じて自分たちのネタを発信し、人気を得るケースが増えてきた。テレビ出演を見て気になってくれた人がYouTubeで動画を検索して自分たちのネタを見に来てくれ、ファンとして定着してくれるだけでなく、動画再生による広告収益にもつながっている。
自分でコンテンツを作って公開するYouTubeは「『自分の得意な見せ方』で勝負できる」と田畑氏は語った。
田畑氏:吉本芸人のガーリーレコードは自分のYouTubeチャンネルを立ち上げて数十万人の(チャンネル)登録者を得ている。メジャーではなくともそれを支持するファンのコミュニティを作り上げ、ニッチな部分で勝負できる(のがメリット)。
『田畑藤本』が運営するYouTubeチャンネル『たばふじちゃんねる』は、2019年9月17日現在で670人の登録者を抱え、ほぼ毎日のペースで新作の動画を公開している。
田畑氏:Twitter上で(YouTube動画の)編集スタッフを募集したところ、3名応募が来た。『(今は)こういう風にして人を集める時代なんだ』と(感慨を抱いた)。
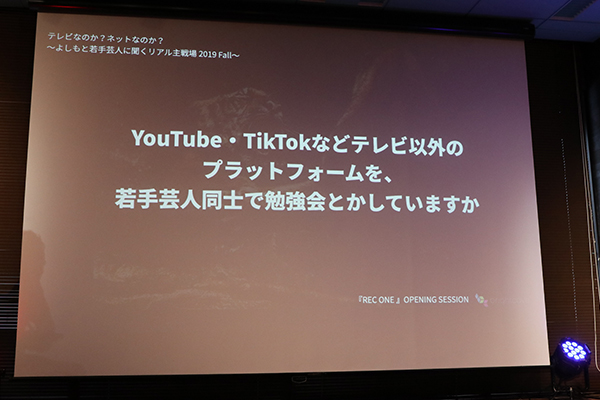
制作スタッフもファンの中から集める、まさにコミュニティベースでの活動がいま若手芸人たちのあいだではトレンドなのだという。「仕事先の楽屋では芸人仲間同士、つねに(効果のある露出テクニックに関して)情報交換を行っている」と田畑氏は語る。
田畑氏:サムネイルはわかりやすくする、(撮影時の)照明は明るめにする、タイトルは短く、ハッシュタグは3つ付ける……など、それぞれ自分たちがうまくいったときのパターンを共有しあっている。お互いをライバル視して競争するというよりも、みんなで(認知されて共に)売れていこうという思いが強い。
■YouTuberの存在は「悔しいけれど、無視できない」
現在は、劇場でのライブ活動を中心とする「田畑藤本」。YouTubeを始めとするWEBメディアで人気を集めるYouTuberのような「配信者」たちにはどんな思いを抱えているのか。
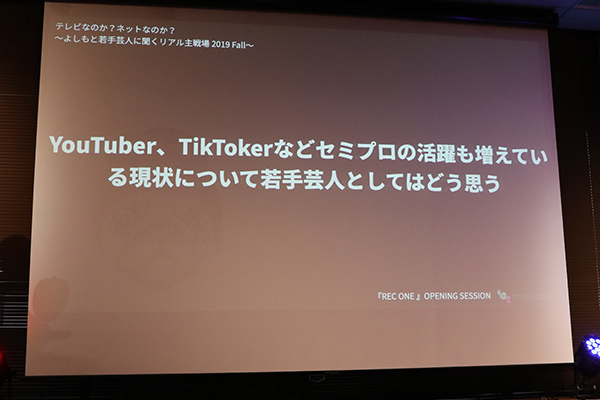
田畑氏:これまで自分たちは舞台の上で芸を見せ続けることで人気を積み重ねてきたが、こうした努力の積み重ねをひょいと通り抜けてYouTuberが大きな人気を得ているのを見ていると、正直悔しく思う部分もある。
しかし同時に、YouTubeやSNSによって得られる認知のパワーは無視できないと田畑氏は語る。
田畑氏:今は芸人がYouTubeでチャンネル登録者を増やして劇場へ足を運んでくれるファンを増やす時代。YouTube上で人気の芸人がライブ告知をしたらチケットが即完売して、芸人仲間のあいだでどよめきが起きた。自分たちのライブを見に来てくれるお客さんにアンケートをとっても、『Instagramの投稿を見て来た』という回答を多く見かけるようになった。
■WEBメディアを通じて「小さな経済が生まれてきている」
田畑氏は、今後の若手芸人たちの「生き残り」に向け、自らの特性に合ったメディアの選択やそれぞれのメディアの特性に合わせた“見せ方”のチューニングについても言及した。

田畑氏:周り(の芸人たち)からは『Instagramではバズるが(同じネタでも)YouTubeではバズらない』という声も聞く。とりあえずいろんなメディア(での発信)を試して、自分たちに合うものを精査している状況だ。
プロもアマチュアも同じ土俵のもと「自分の得意な方法」でアピールすることができるWEBメディアに、田畑氏は大きな可能性を感じているという。
田畑氏:身の回りにはeスポーツ動画の配信で収益を得ている人間がいる。これを受けて吉本興業もeSportsイベントに会場を提供するようになるなど、新しい潮流が生まれてきている。自分もnote(ピースオブケイク社が運営する、個人向けオウンドメディアサービス)を使用し、情報を発信している。WEBメディアの登場によって『(ファンコミュニティを軸とした)小さい経済』がどんどん生まれている感じがする。
個人ベースでの情報発信に大きな門戸を開いたWEBメディアの存在は、これまでスポットライトの当たりにくい存在であった人々のあいだにも経済を生み出している。「新たな潮流」という言葉では表現しきれない “現実”を文字通り実感させられる、約30分のセッションとなった。